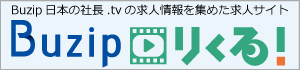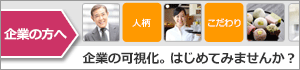1. 保険会社と裁判での基準の違い
交通事故の損害賠償額を算定する際には、大きく分けて「自賠責保険基準」「任意保険会社の基準」「裁判基準」の三つが存在します。一般的に、自賠責基準が最も低額で、裁判基準が最も高額です。
そのため、保険会社から提示された条件が妥当かどうかを精査し、不利益がある場合には裁判基準をもとに交渉していくことが重要です。
2. 医療機関の選び方
はり・きゅう院や整骨院など、医師免許を持たない施設での施術は「治療」とは認められず、「健康増進」や「リハビリ」と判断される場合があります。
この場合、治療費の請求が困難になることもあるため、交通事故後の受診は必ず医師がいる医療機関を選ぶことをおすすめします。
3. 後遺障害等級の認定
治療を継続してもこれ以上改善が見込めない状態を「症状固定」と呼びます。この段階からは、後遺障害の補償に切り替えて手続きを進めることになります。
ただし、申請書類の不備や証拠不足により「非該当」とされたり、本来より低い等級に判定されてしまうリスクもあります。専門家に相談しながら進めることで、適正な認定を受けられる可能性が高まります。
4. 慰謝料の算定時期
入通院慰謝料は、実際に通院や入院をした日数に基づいて算定されます。そのため、治療が続いている間は慰謝料の金額が確定できません。
治療の終了、または症状固定と判断された段階で慰謝料の算定が可能となり、示談交渉もこの時点から本格的に始まります。
5. 能登豊和弁護士に依頼するメリットと適切なタイミング
弁護士に依頼する最大のメリットは「不利益を防ぐこと」です。保険会社からの提案が明らかに不利に感じられる場合はもちろん、「条件が提示された直後」に相談するのも有効です。
専門家に早い段階で確認してもらうことで、適正な補償を受けられる可能性が大きく高まります。